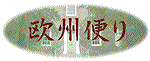 |
|
「元ウィーンフィルのコンマスが指揮すると
」
|
|
元ウィーンフィルのコンンマスが指揮すると 東響がウィーンフィルになった! 音楽会通信 96年11月9日記 野村和寿 |
|
これから不定期で、よかった演奏会についての感想を簡単なメモにして、メールしようと考えました。
長文恐縮ですがおつきあいいただき、一言でも構いませんがなにかご感想いただければ、望外の喜びです。
|
|
東京交響楽団 東京芸術劇場シリ−ズ第29回
96年11月9日 土曜日 午後6時 東京芸術劇場 3階LBI列2番(B席 )4000円 指揮 エ−リッヒ・ビンダ−(Erich Binder) ピアノ 梯剛之 (Takeshi Kakehasi) 曲目 ウェ−ベルン:パッサカリア作品1 ベ−ト−ヴェン ピアノ協奏曲第1番ハ長調作品15 R.シュトラウス 交響詩「英雄の生涯」作品40 ソロ・小森谷巧 |
|
こんな演奏会が日本で聴けるとは、信じられないという感じ、ものすごくオ−バ−かもしれないけれど、ウィ−ンフィルみたいな音がする瞬間さえあった。
|
|
まず、ビンダ−は、オ−ケストラの配置をウィ−ンフィル風に、ファ−ストとセ
カンドバイオリンを、指揮者の左右に振り分け、ビオラをいつものセカンドの位置 においたことで、こんなにビオラが芳醇になるとは驚いた。セカンドバイオリンに
ビンダ−が指示を出していたのにも驚いた。普通、あんまりセカンドに指示をだすなんてことはないし、ベ−ト−ベンとかリヒャルトになると、ものすごくセカンド
が大事になる。 いちばん涙がでるくらいおどろいたのは音楽の始まるときの自然なことだ。音楽 が回りにもうすぐそばに浮遊していて、それの続きで音楽が始まるというくらいの感じ。
|
|
ベ−ト−ベンのコンチェルトのあの長い長い序奏の始まりも、バイオリンは最初の音をだすのに、ものすごく注意していた。いつもは、序奏の部分は、なにか、前
菜またいにやるのが普通なのが、この日は違っていた。1番のコンチェルトはピア ノとオケと両方とも大事なのだとでもいいたいように、ここいらへんが、4番とか
5番「皇帝」などのようなビルティオ−ソ的な曲とは違って、どちらかといえば 、モ−ツアルトに近い感じだ。
|
|
静かにしかにピアニシモであれだけ静かなのに強い音、生きている音が出る。こ
れは高級品と思ってしまう。その瞬間、おもわず、涙してしまった。そのくらい 、コンチェルトの最初のバイオリンはきれいだった。盲目のピアニスト梯の演奏も
それで、ものすごくまじめに、音楽を骨格できかせていた。ちょうどゲルバ−みたいな打鍵のしっかりとした構成感がよかった。ウィ−ンで勉強中のまだ、19歳の彼が、全身でひくベ−ト−ベンにも滋味がいっぱい含まれていた。ひとつひとつを
大切にする、効果的には弾かない。それよりも集中して音を出す、清い潔癖なまで に。
|
|
ビンダ−は、70年台から80年台にかけて、ウィ−ンフィルのコンサ−トマス
タ−をしていた。よく、バ−ンスタインやベ−ムの指揮のビデオでムジ−クフェラ インで、ヘッツェルの隣のトップサイドで、弾いている姿が映る。カルロス・クラ
イバ−のときの、思いっきり溌剌とした、ひっちゃきになったいたずらっこみたい な演奏ぶりとか、ベ−ムのときの、ベ−ムの音楽についていこうとする、非常に深
刻そうな姿が思い浮かぶ。そういえば、ベ−ムは「英雄の生涯」が得意だった。ビ ンダ−も「英雄の生涯」をベ−ムのように振った。非常に翌似ているのは、音楽が
鋭角的でなく、まるでオペラをみているように、芝居的で、視覚的だということ 。リヒャルトには、交響詩というジャンルは、これはもうオ−ケストラでオペラを
作っているのではと思 うほどに充実していた。いろいろな音が含まれていて、それが泡のようにでてきて は消えていくようだ。ビンダ−は、ことさら、楽器をル−ペでのぞきこむようなこ
とをしない。いつもNHKのカメラワ−クのようにソロのところにくると、アップ になるというようなあの感じ。それがぜんぜんない。むしろ、ソロを出すとか、回
りを小さくするというのではなくて、もっぱら、みんなに自由にふかせることで 、楽器のソロが出てくると、これが自然に浮き立つように譜面には書いてあるとで
も言いたげな感じ。自然にフル−トのソロになると際立ってくる。これは不思議。
|
|
「英雄の生涯」は、昔、シュワルベがコンマスをしていたころのカラヤンの来日
した折りの演奏を思い出した。きれいなのが、ソリストとしてではなくて、オ−ケ ストラの中で、とても オ−ケストラの一員として、弾くコンマスのソロとでもいうのだろうか。小森谷の
演奏は、細部までものすごく細かいのだが、それでも全体にわたってそんな感じが 溢れていた。
それにしてもこんなにオ−ケストラが美しく、鳴るなんて。それはちょうど、出 来合いの料理がいつもの演奏だとしたら、その場で作ってみせる、音楽をその場で 構築してみせる芸とでもいったほうがいいかもしれない。録音でいうならば、リビングステレオやデッカのEMIの60年代の録音のように、ことさら、めだたせる のではなくて、団子状かもしれないけれど、音楽全体がこちらに迫ってくるという 感じ。さらに楽しみながら味わいながら演奏を聴いていくという感じ。 |
|
思えば、ウェ−ベルンをあれほど、柔らかに演奏したのも、ウィ−ン節ならでは
であり、ベ−ト−ベンももちろん、ウィ−ンにちなんでいるし、リヒャルトも長く ウィ−ンフィルを指揮していて、長い長い節まわしの伝統が音楽にしみついている
ようだった。
|
| オ−ケストラの演奏は一口にいえば、滋味にあふれている。とても優しい。どう してだろうとばかり考えながら聴いていく。すると、4つにふるときに、3拍と 4拍の振り方がものすごく、場所によって異なる。思いっきり4つにふるときと 、はしょっって、次ぎにいくところとがある。リズムはリズム、メロディ−はメロ ディ−ではなくて、リズムとメロディ−が合体した感じ。だから、有名なメロディ −にいくときに、日本のやりかた、これはおそらくレコ−ドの影響が強いと思うの だが、メロディ−のとろにいくと、いかにもメロディ−が始まりますよとばかりに 、演奏の輪郭を際立たせる、こういうやりかたではなくて、メロディ−に鳴る前の つなぎの部分をだいじにしているので、かえって、メロディ−になるとことがきわめて自然に聴こえるのだ。 |
|
今までの音楽 メロディ−になるとメロディ−が始まる。終わると、なんか手持
ち無沙汰、次のメロディ−になると、また熱心。というのではなく、音楽は流れて いるということ。及び、リズムとメロディ−の融合。柔らかさ。メロディ−を支え
る内声部の充実。楽器がなっているというのではなくて、楽器と楽器が溶け合って、ひとつになるという感じの音。こんなふうな指揮者はいったい日本に生まれるの
だろうか。
|
| 頭によぎったこと。それは、日本は、勘違いをしているのではないか。それは 、オ−ディオにもまったくいえることで、いい音ということと、音楽が聴こえると いうことがまったくむすびついていないという状況は、日本のまじめさに対する 、ヨ−ロッパのすごいけれど、どこか違っているということがよくいわれるが、ま さにあれ、という感じだ。 |
|
指揮者というのは、メロディ−のところで、メロディ−をきかせるのではなくて
、メロディ−のところまでにいかに素晴らしい状態に周囲をもっていくかにあるのではないか。
|