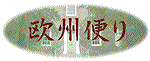 |
|
キーロフオペラの「オテロ」
|
|
キーロフオペラの「オテロ」 何でも自前でやろうとがんばる やる気が感動の源泉! みなさま またまた、音楽会通信2をお届けいたします。 もし感想をおきかせいただけましたら、望外の喜びです。 |
|
96年11月12日 野村和寿
|
|
オテロ 全4幕 11月10日 午後6時開演
サンクト・ペテルブルク・マリインスキ−劇場キ−ロフオペラ日本公演 脚本:アリゴ・ボ−イ ト 原作:ウィリアム・シェイクスピア(イタリア語による上演) 指揮:ワレリ −・ゲルギエフ 演出:ジャンカルロ・デル・モナコ(マリオデル・モナコの息子 )、 美術:ウォルフ・ミュンツアァ−(舞台美術はドイツ・ボン歌劇場製作) オテロ:ウラジ−ミル・ガル−ジン、 オテロの妻デズデ−モナ:ガリ−ナ・コルチャコ−ワ ヤ−ゴ:ニコライ・プチ−リン、 カッシオ:ユ−リ−・アレクセ−エフ サンクト・ペテルブルク・マリインスキ−劇場キ−ロフオペラ管弦楽団・合唱団 第1幕35分 休憩15分 第2幕35分 休憩20分 第3幕40分 第4幕 35分 終演予定 午後9時半 3階R−2列16番 C席 18,000円 |
|
突然のように「オテロ」をみたくなって、招聘元のジャパンア−ツに電話。きっとそんな人が多いようで、留守番電話で、今日の当日券の案内
が流れていた。16時15分当日券が売り出された。NHKホ−ルの横の当日券売 り場に並んだのは、私を含めて、5人だったが、ひとまず、C券を買うことができ
た。16時30分早々と会場。突き当たりの北ホ−ルで、永竹由幸氏のプレト−ク が始まっていた。永竹氏の講演の内容は、当時のベネチアに当時、黒人は存在したかというテ−マで、しっかり当時の文献から、そんなに偉い人の話ではないけれど
、オテロのモデルが存在したこと、回教の国であるアフリカとキリスト教の人間は 14−5世紀には、意外と自由に結婚が認められていたことが話された。だから、ベネチアからキプロスに派遣されている総督が、黒人である可能性がゼロではなかっただろう。もちろん、数は少なかったのに違いないだろうが。といういかにもオペラ好きが好きそうな非常にオタク的テ−マ。それと、劇の中で問題となるハンカチについて、なぜ、ただのハン
カチがそんなに重要なのかについての謎、あのハンカチは回教の国では、人、物の 刺しゅうが禁じられていたので、デザイン的な刺しゅうがされており、原作では
、それを、女中が写し取るということに随分時間をとるくだりがあること。遠く離 れたシェ−クスピアが、この原作をどうやってみつけたかとか、イギリスの人にわ
かりやすくするために、地位を総督にしたとかということだった。
|
|
永竹氏の話はそれにとどまらず、ベルディの音楽についてもふれ、アイ−ダで
、ポピュラ−的になった後、オテロ、そして、ファルスタッフへと、音楽が充実す る陰に女性の存在があったことを指摘していた。ぼくは、このところ、ファルスタ
ッフを見、またトラビア−タをみる機会があったのだが、ベルディの音楽は単に劇 につける伴奏というのではなくて、もっともっといろいろな意味を音楽に見いだせ
るように思えてならない。
|
|
演奏会の前のアペリティフとして、時間がゆっくりと流れていく。前日のオ−ケストラの時と違うのは、今日のは、オ−ケストラと演出と舞台上のコ−ラス
、ソリストの一体となった総合芸術だということ。それを統括している指揮者とい う存在。しかもマリインスキ−劇場あの、チャイコフスキ−の交響曲とかの初演でも有名な由緒ある劇場こそが、キ−ロフ・オペラ、しかもゲストを一人も使わないで、全部自前で行うというおそらく世界でただ一つの劇場。舞台を見たあと、やは
り、ロシアという国は、たとえ、食物がなくても、芸術は本当に生きているのだなということ。お金をたくさんとる歌手を多くかかえていることができる、メトとか
、昔のさん然と輝く伝統をもつ、ミラノやコベント・ガ−デンとは違い、たとえ 、歌手は、そんなに有名でなくても、全部を自分たちでやっていこうとする姿勢がすごくいい。しかも今日
、デズデモナを歌ったコルチャコ−ワのように、ここの歌手から西で脚光を浴びているひとたちも出てきていて、もう伸び盛りの歌手と舞台をみることができた。
|
|
それにしてもどうして、オテロは何度見ても、そのたびに胸が熱くなるのだろうか。そして、それは、物語に潜むいろいろな意味あいによるところが大きいに違
いない。たしか、86年にクライバ−のミラノでみたときは、クライバ−のめのさ めるような指揮にうっとりしていただけだった。しかし、今回は、音楽にうちのめ
され、自分の心情に気持ちが発展し、果ては、何度もみたくなってしまうという 、激情にかられてしまった。
|
|
6時開演、最初から驚きの群衆の声、3階まで、地をはうようなバス、それに
まけんばかりのアルトの歌・歌・歌。やや耳をつんざくかのように聴こえてくる 。面白いのは、合唱の群衆の配置で、かならず、バスが右、テノ−ルが左、とかた
まりになってきこえるように配置していた。でもなんだか、ロシアのコ−ラスは 、ボリスゴドノフのような野太い声にも聴こえてしまうと、そう思ったのもつかの
ま、観客のほうを向いて歌う群衆は、ドラマを観客に導入する船頭の役に思えてき た。
|
|
キ−ロフのシェフ、ゲルギエフは若干43歳、指揮棒をもたずに、手の指をい
っぱいに使って、音楽を表現する。手はものすごく大きいみたい。このオペラは純粋さの乙女、悪魔 嫉妬 妬み、虚栄、はかなき野望など原作者シェイクスピアが
得意とするジャンルが生きている。ヤ−ゴという悪玉をいかにもにくにくしげにど う歌うか。これは、もうヤ−ゴのためのオペラといっていいくらい、悪巧みは、音
楽によって、倍加され、悪く悪く聴こえてくる。
|
| 第4幕デズデモナの歌う「柳の歌」、最初にコントラバスの長い長い死を予感 させるソロ、続いてビオラの和音と続くところ、どこか宗教的な側面にくると、必 ずといってよいほど、転調を繰り返し、長調になる。宗教的な音楽は、時として 、ベルディの「レクイエム」みたいだ。 |
|
ゲルギエフはいったい、どんな執念をもっているのだろうか。手を小刻みに動
かしつつ、正に突進していく感じ。「柳の歌」の場面は、どことなく、淡白で東洋 的な旋律、淡々と死への予感を歌えばうたうほどに、悲しみが周囲を圧倒し、次の
オテロの登場とともに、クライマックスに一気に達する。しかもゲルギエフのすご いのは、クライマックスですよと大きな身振りをするのではなくて、どんどんどん
どん高めていくと、オ−ケストラの方で自然に高まっていくのである。おおげさな 指揮ぶりではない。
|
|
ベルディは歌とオ−ケストラの両方に意味をもたせつつ進む。1つ1つのフレ
−ジングは、それぞれ、劇の中の意味をしっかりととらえているばかりでなく、そ れ自体が、大きなメッセ−ジにもなっている。離合集散が一気に起こり、オ−ケス
トラは、その度に高鳴り、一気に高見に達する。そうして、潮がひくように、すぐ に引っ込む。そのつぼをわきまえているのが、日本のオ−ケストラとの大きな違い
である。
|
|
いや、もしかすると、キ−ロフのオペラのオ−ケストラは、世界でいちばん
、表現にたけているのかもしれない。人間の欲望とか、虚栄だとか、妬みとか、い ろいろな業、そして、はかない、どうしようもない、愛とその反対の嫉妬との裏腹の関係をさらけ出す、オテロという人間のものすごく深いところに迫る劇的表現
。これを音楽ともども、こころをあおられたのだからもうたまらない。人間の弱さ 、はかなさ、悪魔の存在。
|
|
5時半の開場とともに、3階の席へ向かう扉を開けると、ピットでは若いTシ
ャツを着た青年が、非常に美しいバイオリンの音を響かせていた。というより単に 練習をしていただけなのだが、その逼迫したような、迫ってくるバイオリンの旋律にはドラマを感じさせた。その彼はコントラバスのすぐ前の席に座っていた。歌心
をもったバイオリニストがいる。これはいい「オテロ」になりそうだ。と予感した 。全舞台が終了すると、ピットの中は、もう帰り支度を始め、席をたったようにみ
えた。しかし、そうではなかった。舞台に近いところでは、舞台上の衣装とか、歌手たちの一挙手一等足がみえないので、ピットの中の客席寄りにオ−ケストラの団
員は移動したのだった。毎日の舞台に心から拍手をおくる、オ−ケストラのプレ −ヤ−。カ−テンコ− ルは、幕間には一度も行われずに、歌手と演じる者の区別をはっきりとさせていた
舞台は、今度は歌手たちが、菱形にオテロを中央に居並び、そこにゲルギエフを迎 えにいく女性歌手陣、すごい舞台だった。時計は21時半をまわっていた。
|
|
舞台劇は終了とともに、また始まりでもある。何か。「オテロ」が終わった瞬間 にまた、見た くなってしまう。これはタルコフスキ−の映画でもいえたことだった。家にある LDで、ゴッピのヤ−ゴ、トゥッチのデズデモナ、モナコのオテロのやつ(59年 のイタリア歌劇団の公演)、テバルディのデズデモナのやつ(62年のドイツ・オ ペラのライブ、指揮はパタ−ネ)、ドミンゴのオテロ、リッチャレッリのデズデモ ナのやつ(ゼッフィレッリの 「柳の歌」をカットした映画版、オケはミラノ・スカラ座、指揮はマゼ−ル)と 、立て続けに4幕を見てしまった。 |
|
欧州便り 目次 Nomuwrites
|